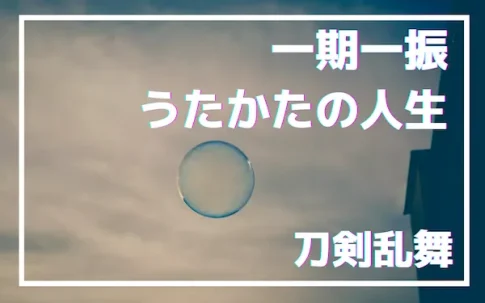現在アニメ2期が放送中の『昭和元禄落語心中』。
原作は人気BL作家でもある雲田はるこ先生による、噺家(はなしか)たちの生き様を描いた本格落語漫画です。
第17回(2013年度)文化庁メディア芸術祭マンガ部門で優秀賞、
第38回(2014年度)講談社漫画賞(一般部門)を受賞と、高い評価を得ています。
2期に渡りアニメ化中の『落語心中』は、BL作家でもある雲田はるこ先生により描かれた麗しい男性噺家たちが、多くのファンを魅了しています。
しかしこの作品の魅力はキャラクターの美しさだけではありません。
その本当の魅力は、読者に自然に伝わってくる落語の面白さや深さに加え、繊細に描かれた噺家の業が錯綜(さくそう)する構成にあります。
今回は『八雲と助六編』をご紹介。
主人公が崇拝する八雲師匠の秘められた過去から、人間の逃れられない性について解説します。

『昭和元禄落語心中』のキーマン・与太郎が敬愛する師匠”八雲”の秘められた過去
主人公の与太郎は、昭和最後の大名人と言われた噺家・八雲が演じた落語「死神」を服役中に見て、落語家になると決心します。
満期で出所すると、与太郎は真っ先に寄席に向かい、八雲に弟子入りを志願。
今まで弟子を一切とってこなかった八雲でしたが、なぜか与太郎が弟子になることを認めます。その日から八雲の家に住み込み、高座にも上がるようになっていきました。
八雲の家に居候することになった与太郎は、同居する八雲の養女・小夏がかつて一世を風靡した”助六”という噺家の娘であると知ります。
小夏が八雲と言い争った日、小夏が
有楽亭助六はお前が殺したんだ
と言うのを聞いた与太郎。
その理由を与太郎は知る由もありませんでしたが、助六と八雲の間に何やら深い因縁があることだけは確かなようです。
ある日、八雲の独演会中、与太郎は舞台袖でまさかの居眠り。
八雲に破門を言いつけられた与太郎ですが、平謝りの末、八雲からこんなことを言われます。
破門しねぇ代わりに
なァ与太郎?
アタシ達ゃあ
みっつ約束しなけりゃならないよ
三つの約束と引き換えに八雲の元で居させてもらえることになった与太郎。
一つ目は、八雲と助六の落語を覚えること。二つ目は”助六”と関係することでした。
八雲「助六と約束して果たせなかった事がある
『二人で落語の生き延びる道を作ろう』ってね
どっちかが一人欠けたってできねぇ事なんだ
だからこの穴埋めておくれ
それがふたぁつ」
与太郎「そんなでけえ約束…できんのかな」
八雲「できねぇ時?その時ゃ諸共心中だよ」
与太郎「あとひとっつは?」
八雲「絶対にアタシより先に死なねぇ事」
涙ぐむ与太郎と、その場にいた小夏に八雲はこう言います。
「じゃあひとつ、お前さん方に話して聞かしてやろうか
あの人とアタシの約束の噺をさ
長ぇ夜になりそうだ、覚悟しな…」
こうして八雲師匠の秘められた過去『八雲と助六編』が始まります。
八雲の過去と助六との因縁を明らかにする”八雲と助六編”
怪我で足が不自由になった幼少期の八雲。
芸者の女系一族に生まれ、踊りもできなくなった八雲は、捨てられるように先代の八雲である七代目八雲の家に養子に出されます。
そして同じ日、貧しい身なりをした同年代の男の子が入門してきました。入門の動機を聞かれ
「八雲(七代目)になりてぇからだ
その大名跡は七代目(おいちゃん)からしか貰えねぇんだろ」
と言った少年は孤児。後に”助六”となる信さんでした。
若き日の八雲は”菊比古”という前座名を師匠からもらい高座に上がるようになりますが、折しも世間は第二次世界大戦へと突入していきます。
戦争で兄弟子たちがどんどん八雲門下を去っていく中、信さんだけは
「こんなご時世だからこそ、絶対に落語を残しといてやらなきゃならねぇぞ
腹いっぱいになりゃ、また皆、寄席に戻ってきてくれる
俺ァ絶対そう信じてるよ」
と落語が今後、必ず大衆に必要とされるはずだと確信していました。
信さんの言葉通り、戦争の時代が終わると、寄席に次々とお客さんが戻ってくるようになります。
「そら来たぜ!見ろよこの客、俺の言った通りになったろ
俺たちの時代が、もう来てるんだよ」
輝いた目でお客さんの様子を眺める助六を見て、菊比古は思います。
この人の見つめる先はいつも明るい
そして正しい
私も同じ方を見ていれば
自ずと自分の行く道も見える。
そう確信したのでございます。
”欲深き、人の心と降る雪は”に見え隠れる人気噺家たちの本性
しかし一方で、前座の頃から菊比古は自身の落語の方向性が見いだせず、苦しい修業生活を送っていました。
さらに父親でもある師匠が他家から引き取った手前、高等科までは通わせたいと思っていたため、菊比古は学校に行きながら落語を練習する生活。
昼は学校、夜は寄席という忙しい毎日の中で、朝から晩まで落語漬けの信さんとの力量の差はどんどん開いていきます。
菊比古が心から尊敬し、憧れていた信さん。
しかし敬愛の心とは裏腹な、敵わない実力に対する焦りと妬みも菊比古を苦しめていきました。
一方の信さんにも、胸に秘めた野望がありました。
菊比古「『助六』?」
信さん(助六)「おうよ、寄せ場で世話になってたジジィの名前なんだ。
天狗連(※芸好きな素人衆の集まり)でテメエで付けてた高座名なんだけどよ
皆そう呼ぶんだけど誰も本名知らねぇんだ
だから俺で二代目
この助六さんが先代…師匠(七代目)の前の八雲師に弟子入りしてたんだってよ
でも何かでそれは挫折して
露頭に迷って寄せ場に流れついて
俺を拾って育ててくれたんだ
師匠だって会ってるはずなんだよ
だけど顔も覚えちゃうねぇだろ
かたや大名人、かたや寄せ場でのたれ死に
俺は怖い、いつか自分もそうなるんじゃねぇかって
だから絶対に八雲になるって決めて門をくぐったんだ
面白ェだろ、死んだ『助六』が八雲になるんだ」
寄せ場で育った自分が八雲を継ぐという、信さんの野望。
幼くして自ら八雲の門を叩き、「八雲になりたい」と断言していた信さんの心には亡き養父・助六の無念を晴らすべく、八雲を継ぎたいという願望があったのでした。
同時に古い仕来たりや礼儀作法を毛嫌いする信さんは助六となってからも、自分のやりたいようにしたいという欲望が抑えられず、先達の名人噺家たちから目を付けられるようになってしまいます。
助六の唯一の味方は、熱狂的なファンたちと、幼いときから人生を共にしてきた伴侶のような存在・菊比古。
しかしその菊比古も決して無欲だった訳ではありません。
「信さんは師匠のお傍でずっと修業できる。
これ以上差がついちまうのは嫌だ」
「遊んでんのに仕事ももらえて、信さんばっかりずるい」
時々漏らされる、助六の恵まれた才能や恵まれた環境を妬むような言葉。
こういった台詞からも彼の深層心理には、噺家として成功したいという欲の心があったことがわかります。
戦後、落語ブームが訪れ、助六は若手の中では一番の注目株となり、人気絶頂に。
そんなある日、観客の大きな声援を受けながら演じたのは、「夢金」という噺でした。
「エー我々の方でよくしみったれ、ケチの噺なんてのを致しますが……
『欲深き、人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘るる』…
なんてんでね、とくにひでぇのは寝言でもっても金のことばっかり。
『百両ォ欲しい~』…」
この噺の冒頭に助六が言った
「欲深き人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘るる」という歌。
これは助六たちが密かに抱えている、積雪のように深い欲の心を表現しているようでもあります。
落語「夢金」冒頭の狂歌に表れている助六たちの実態
強欲な男・熊蔵が、人殺しから女性を助けたことにより大金を手に入れるが、すべては夢だったという結末の落語が「夢金」。
熊蔵が登場する前に
「欲深き人の心と降る雪は積もるにつけて道を忘るる」
という狂歌を冒頭に振ることがある噺です。
この狂歌は「幕末の三舟」のひとり、高橋泥舟(でいしゅう)が残した歌とされています。
「欲」という心は、仏教で教えられる煩悩の一つです。
煩悩というのは漢字の通り、私たちを煩わせ悩ませる心のことで、中でも最も私たちの心を惑わせるのが欲の心と教えられています。
「道を忘るる」というのは、道理を忘れてしまうということでしょう。
うず高く積もる雪のように、欲の心は限りがない。
そして苦しみから迷い、時には道理を忘れてしまうほどの過ちを犯してしまう。
そんな、 欲によって苦しんでいる私たち人間の実態を表現しているのが、この狂歌なのです。
そしてこの狂歌を高座で口にした助六自身の人生も、欲の心をはじめとする煩悩が”積もる”につけて、混迷を極めていきます。
助六はどのように「道を忘るる」方向へ向かっていったのか。
次回に続きます。
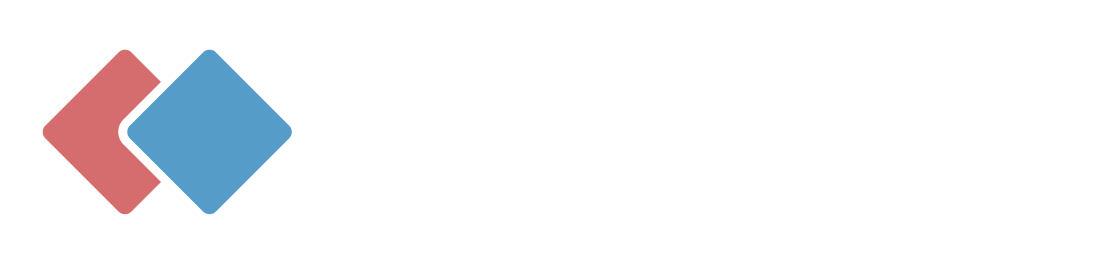





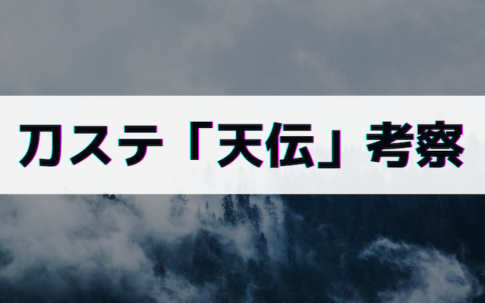






-485x323.jpg)