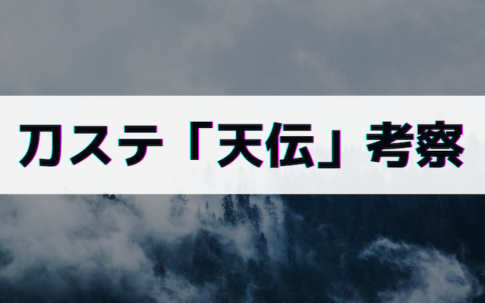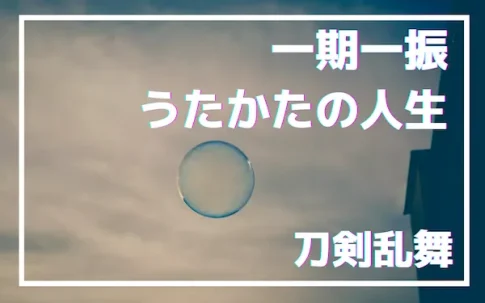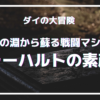雲田はるこ先生による本格落語漫画『昭和元禄落語心中』の一つの象徴を表すシーン。
それは死んだ噺家・助六の亡霊が出てくるシーンです。
物語の最初の時点で既に助六は故人なので、回想パートか亡霊でしか登場しないのですが、佇むだけの助六の姿は意味深です。
主人公・与太郎が名人噺家・八代目八雲に弟子入りして噺家になる姿を描いたこの作品で、偉大な師匠として登場するのが八代目有楽亭八雲。
八雲は死んで十年以上経っても助六に心を囚われており、さながらそれは「助六の呪い」のよう。
前回記事では先代の八雲である、七代目八雲の苦悩を通して考察しました。
今回は八代目八雲が抱える「助六の呪い」の正体に迫ります。
※ストーリーの核心部分に関する記載があります。ネタバレご注意ください。

『昭和元禄落語心中』ネタバレあらすじ 八雲を苦しめる「助六の呪い」
先代の七代目八雲は若い頃、六代目の息子である自分よりも落語の才のある「助六」という噺家に敵意を燃やし、息子という地位を使って八雲を継ぎ、助六を蹴落とします。
落語界を去った助六は寄せ場でのたれ死んだのですが、七代目八雲として活躍していたある日、「八雲になりてぇ」という少年が現れます。
その落語は自分が追放した噺家・助六の生き写し。寄せ場で死んだ助六が育てた子だったのです。
やがて少年は噺家としての才能に開花し、「助六」を高座名にしたいと言い出します。
助六を名乗りてェと言われた日にゃ生きた心地がしなかった
因果応報・・・俺んとこにあいつが来たのも因縁なんだ
七代目八雲にとって助六は、過去に犯した悪行の報い、因果応報の象徴でした。
そして八代目八雲にとっては兄弟のような存在だった二代目の助六。
八雲は憧れながらも、自分より噺家として大成していく助六に妬みの心を抱いていました。
どちらが八雲を継ぐかと周囲に思われていた折、助六は師匠と大喧嘩し破門されてしまいます。
助六と八雲の元恋人でもあるみよ吉は二人で田舎に逃げ、八雲は二人を更生させようと追いかけますが、不幸な事件が発生。
助六は愛した妻・みよ吉に刺された上、一緒に転落死したのです。
この話を八雲が主人公の与太郎に語った十年後。八雲が先代の墓参りに来ていたところに、助六の亡霊がまた現れます。
いつも同じような微笑みを浮かべ、虚ろな瞳をして佇む助六。
「なあ、何か喋りやがれ、噺家だろッ…
そのカオは何かい、老いぼれを笑ってんのかェ
そいともそれは怒ってるってェのかい?」
「師匠ッ」
その声は、与太郎でした。
与太郎が現れた瞬間、助六の亡霊はパッと姿を消します。
頑なに弟子を取ってこなかった八雲が、何の気まぐれか弟子にした与太郎。その屈託のない笑顔はまるで「助六の呪い」を吹き飛ばすかのようで、八雲の表情もふっと和らぎます。
そもそも与太郎という高座名は落語の噺の中でよく出てくる名前で、バカで間抜けな男という意味。
決して良い意味ではない名前ですっかり有名になった与太郎ですが、八雲がそのことに触れると
「ししょーがくださった名前ですから!」
と可愛いことを言う与太郎。
しかしそんな彼から思いもよらぬ一言が。
「ししょー
ずっとずっと言いたかったことがあるんです
助六を継がせてください」
固まる八雲の脳裏に浮かんだのは、微笑む助六の亡霊でした。
与太郎が現れるといつも助六は消える。
まるで八雲にとって救いのような存在に見えた与太郎が、八雲ではなく助六を継ぎたいと言った…
「助六の呪い」である因果応報は八代目八雲にも降り掛かったのです。
与太郎も苦しむ「因果応報」八雲が授けたアドバイスとは
一方、助六を継いだ与太郎にも思わぬ災難が。
元ヤクザだったという与太郎の過去が週刊誌で取り上げられ、スクープされてしまいます。
その悪影響は師匠の八雲にまで及び、頭を下げる与太郎に八雲はこう言います。
八雲「背中の彫り物みせてみな」
与太郎「みっともねえ古傷で…」
八雲「何だエ筋彫りだけど、見事な鯉金じゃねえか
お前さんはこれから過去としっかり向き合わないとならねぇ
決別じゃなくて抱えて生きろ、罪を忘れるな
それが人間の業ってもんさ」
その言葉で前を向けるようになった与太郎は少しずつ自分の落語を見つけ、名人噺家へと大成していきます。
一方八雲は
落語と心中、それがアタシの定めさ
と口癖のように言い続け、高座の最中にみよ吉の亡霊を見て倒れます。
体が弱り、しばらく落語を離れていた八雲は、終演後の寄席に訪れ
最後に一席、付き合っとくれるかい
と独りごち、だれもいない寄席で『死神』を演じます。
そこへ現れたのは助六の亡霊。
最初は今までとは違い八雲に生きていたときのように話しかけますが、途中から様子がおかしくなり、ふと八雲が見上げた眼前にいたのは骸骨の姿をした本物の「死神」でした。
死神にそそのかされてロウソクを投げた八雲は焼死しかけますが、与太郎が駆けつけ、命だけは助かります。
八雲の死後明らかになった「助六」の本心
繰り返し現れる助六とみよ吉の霊に生気を蝕まれるかのように徐々に弱っていき、八雲はその後寝たきりのような生活を送ります。
苦しみに満ちた八雲の生涯でしたが、最期は与太郎の噺をラジオで聴きながら家族に囲まれ、眠るように息を引き取りました。
その後、八雲は死後の世界でホンモノの助六の「亡霊」と会います。
生前何度も浮世に登場していた助六。
さぞかし八雲を呪い殺したかったのかと思いきや、助六の口からは意外な言葉が。
助六「坊(八雲のこと)、見てみろ、この腹の傷。かかあ(みよ吉)にやられた(刺された)ヤツ、お侍みてえだろ、ぶはは」
八雲「笑い事かい、どうしてあんな事したんだい」
助六「笑い事にしねけとやってらんねぇだろ、ばかぁ
本当に刺さっちまいやんのォ
あのかかあしょっちゅうやってんだよオ
包丁持ち出して『死んでやる~っ』ってなア
あの日に限って変なトコで転びやがってほんとにあのバカ…」
八雲「すまなかったよアタシが悪かった
未練がましく迎えになんざ行かなきゃ良かった」
助六「坊が来てくれなきゃあのまま小夏と3人でのたれ死んでただけだ
誰が悪いなんて話は野暮だろ
俺たちの事三方一両損で痛み分けだ
皆が我を通して皆が悪かった」
助六は八雲を恨んでいないばかりか、八雲がいなかったら娘まで死んでいたと八雲に感謝していたのです。
繰り返し八雲の前に出てきたみよ吉も(顔は恐かったですが笑)娘や八雲が気がかりで様子を見に行っていたと打ち明けます。
現世にいくために死神の力を借りたところ、死神が八雲の芸に惚れ込み取り殺そうとしただけで、助六自身には八雲を呪う気持ちはなかったのでした。
皆が我を通して皆が悪かった。
つまり各々が自分の生み出した因果応報の報いで苦しんだだけだった。
「助六の呪い」のように見えた助六の亡霊は、因果応報、つまり自分の過去の行いによって苦しむ八雲の心の象徴だったのです。
どこかに存在する世界ではなく、自分が生み出していく「地獄」
落語には『地獄巡り』という演目がありますが、「地獄」の語源はサンスクリット語の「ナラカ(Naraka)」であり、意味は「牢獄」です(ナラカを音写したのが「奈落」です)。
落語の『地獄巡り』には賽の河原や三途の川など、マンガや映画でも描かれるような「地獄」の世界に関する描写があります。
しかし本当の「 地獄」はどこかにあるお伽噺のような世界ではなく、罪を犯した人が入れられ苦しむ牢獄のような、自分の行いが生み出した苦しみの世界を言います。
八雲が長年、既に死んだ助六に心を縛られて独り苦しんだように、苦しみの原因は自分自身が作り出しているのです。
何かに失敗したり挫折したとき、ふと振り返ってみると、その苦しみは自分の行為が生み出していたことが知らされることもあるでしょう。
自らが生み出した「地獄」に苦しみ続けた八雲でしたが、その苦しみから抜け出す方法は実は知っていました。
助六を継いでからスクープに遭い苦しんでいた与太郎にかけたこの言葉。
お前さんはこれから過去としっかり向き合わないとならねぇ
決別じゃなくて抱えて生きろ、罪を忘れるな
それが人間の業ってもんさ
過去の行いを無かったことはできないが、今の苦しみを生んだ過去としっかり向き合えば、未来の自分が地獄から抜け出すために、「今」できることが見えてくる。
八雲自身は中々実行できなかったことでしたが、与太郎は過去と向き合っていきます。
その後噺家として大成功、八雲が亡き後、九代目・八雲となります。
自分が生み出した地獄から「落語と心中する」と言っていた八雲にとって、与太郎が助六になったのは、助六の呪いが降り掛かったようにしか思えませんでした。
しかし実は、いずれ八雲を継ぐために与太郎は一時、助六を襲名しただけ。
落語の世界を先の先まで見通した与太郎が若い頃に襲名した助六の名は、九代目・八雲となって落語の未来を切り開いたのでした。
過去と向き合うことは八雲ですらできなかった大変難しいことですが、今の苦しみから抜け出すためには、地獄を生み出した根本原因を見つめていくことが不可欠です。
与太郎のように「因果応報」の原因を見つめる目のある人に私もなりたいと思います。
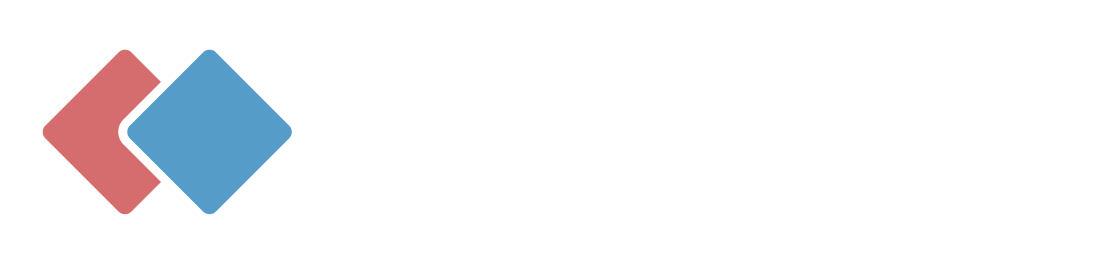












-485x323.jpg)