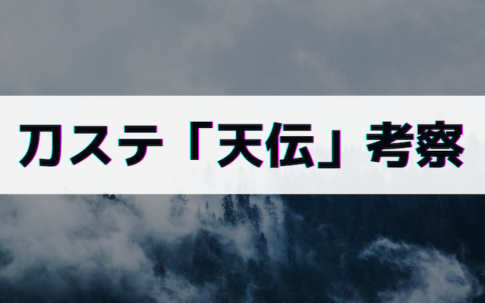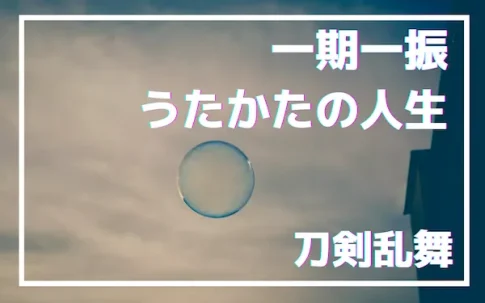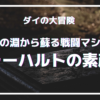望まれた訳ではなく、助けを求められた訳でもない。
ただ、生まれて初めて自分で考えて自分で選んだ目的だったから。
大切にしようと、そう考えただけである。
結果に後悔はない。後は死を待つだけ。
迫り来る死を前に、時間が溶けた飴のように引き延ばされていく。
早くして欲しい、と無意識に願ってしまう。
時間が緩慢であればあるほど、俺は禁忌である問い掛けを思考してしまうから。
ーーーああ。俺は一体、何のために生きていたのだろう。
アニメ放送中の話題作『Fate/Apocrypha』あらすじ ※ネタバレ注意
現在アニメ版第2クールが放送中の『Fate/Apocrypha』。
アプリゲーム『Fate/Grand Order』など様々な超人気コンテンツで広く知られるFateシリーズの外典(アポクリファ)です。
「Fate」といえば、おなじみの外せない軸になる設定が「聖杯戦争」という戦いの場でしょう。
生き残ったただ一組のマスター(魔術師)とサーヴァント(英霊)が手に入れることができる「聖杯」。
どんな願いも叶えることのできるこの聖杯を巡り、聖杯に選ばれし7組のマスターとサーヴァントが殺し合いをする戦争がメインストーリーになりますが、『Fate/Apocrypha』に登場するマスターとサーヴァントはなんと倍の14組です。
Fateで描かれるのは、一般人に紛れ世間の裏側に魔術師たちが跋扈する世界。
魔術の秘匿や管理のための組織・魔術協会により魔術が漏洩することが無いように秩序が保たれていました。
しかしダーニック・プレストーン・ユグドミレニア率いるユグドミレニア一族が魔術協会から離脱、新たな協会の設立を宣言します。
ダーニックは外見は青年ですが中身は97歳の魔術師で、第二次世界大戦の最中に日本の冬木市で行われていた第三次聖杯戦争にナチスドイツ側の魔術師として参戦し、聖杯戦争を行うための魔術炉心・大聖杯を奪ってミレニア城塞に隠匿していました。
半世紀以上に渡って周到な準備を進めたダーニックは、魔術協会に宣戦布告し、襲撃に来た魔術協会のハンターたち50人のうち49人を抹殺します。
ところがダーニック達ユグドミレニアにとって思わぬ誤算が起こりました。
「そこが今回の聖杯戦争の興味深いところでな。
召喚可能なサーヴァントは何と倍の十四騎だ」
「何……?」
「最後に生き残った魔術師、彼はミレニア城塞の地下に眠る大聖杯を発見した。そして、予備システムの開放に成功したのさ」
ユグドミレニア一族が七騎のサーヴァントを一勢力で揃えたことにより、対抗策として大聖杯に仕掛けられた予備システムが発動。
魔術協会も七騎のサーヴァントを召喚することとなったのでした。
ユグドミレニア一族は「黒」陣営、魔術協会は「赤」陣営として前代未聞の規模で繰り広げられることとなった「聖杯大戦」。
しかしダーニックにはもう一つある勝算がありました。
そのもう一つの勝算が、この聖杯大戦を思わぬ展開へ変えていきます。
「生まれたことに意味がなく、存在意義が稼働していない」物語の真の主人公は死ぬために生み出されたホムンクルス
ーーー運命が流転する。変転し、拗れ曲がって狂い出す。
ダーニックのもう一つの勝算は、ユグドミレニア一族の中で屈指の錬金術師ゴルド・ムジーク・ユグドミレニアが編み出した策でした。
聖杯戦争で活躍するサーヴァントは元々生き物ではないので、召喚や生命活動の維持には、マスターである魔術師たちの魔力供給が必要になります。
普通の人間に言い換えれば常に体力を奪われているような状態。
そのリスクを物ともしない策が、錬金術に長けたゴルドによって編み出された魔力を供給するためのホムンクルス(人造人間)を消費してサーヴァントに魔力供給をするという戦略でした。
実は魔力供給には人間の生気も代用できるため、人を誘拐してきて使うという手段も取れるのですが人道的に許されないし犯罪者になってしまいます。
そこで錬金術によってホムンクルスを大量生産し、魔力を供給するためにその生命を使い捨てれば、法で裁かれることもなければ供給源に困ることもない。
これがユグドミレニア一族の秘策でした。
しかし作られたとはいえ、高い技術で生み出されたホムンクルスには人間としての確固たる自己を持つものがありました。
そんなホムンクルス、後にジークという名を自らに付けることになる少年は、水槽の中のような場所で意識を浮上させます。
彼の眼前に、一人の人間と一人の怪物が立っている。
どちらも幾度となく自分の前を通り過ぎた人物だ。
一方の名前は、確かロシェ、あるいはマスター。
もう一方は、キャスター、あるいは先生。
「ーーー魔術回路の組み込みを試してみましょう」
キャスターの言葉に、ロシェが頷いて答えた。
「なら、ここのホムンクルスを使って……」
ロシェとはロシェ・フレイン・ユグドミレニアという人形工学(ドール・エンジニアリング)で名の知れた血筋の魔術師。
そしてキャスターはロシェが召喚したサーヴァントで真名はアヴィケブロン。
ゴーレムの大家として知られる哲学者でした。
その二人が「ここのホムンクルスを使って」と会話をしている。
私たちと変わらない自我を持つジークはその意味を理解してしまいます。
脊髄を蟲が這い回るよう悪寒。過つことのない、確かな死の運命。
ここのホムンクルスを使ってーーー使う、即ち消費。
使えば、得るものがある代わりに消えるものがある。
鋳造されて以来、あらゆる状況で一定回数を保ち続けていた心音が、わずか一分にも満たない会話によって、激しく掻き乱されていく。
創造には消費が伴う。創造されるのが『魔術を使用するゴーレム』ならば、消費されるのは当然『魔術回路を持つホムンクルス』に決まっている。
悪寒の正体を、彼はとうとう理解した。
消費は消滅であり、消滅は即ち『死』。
その言葉を知っていても、理解はできていなかった。
作られた「脳」に知識として備わった「死」という概念。
今から使い捨てられる命という事実を認識したとき、ジークにとって眼前に迫った死は知識として組み込まれたソレとは全く違う自身の問題に激変します。
「まず、三体くらい使ってみましょうか。ええと……これと、これと、これ」
自分が指差された。色鮮やかな死が、彼の心を窒息させるように締め上げる。
目を逸らしていた六割が、厳然と告げた。
ーーーお前は『死』ぬ。
生まれてすぐに、この魔力供給層に封じ込まれて全く何の意味もなく、
ただたまたま目についたからという、ただそれだけの理由で消費される。
生まれてすぐ向き合うこととなった自身の「死」。ジークに芽生えた「生まれた意味を知りたい」という思いが運命を変えていく
二人が去っていく。
自分が死ぬまで、あと少しの猶予しかないと確信した。
絶望が襲いかかる。目を逸らし続けていたのはこれだ、これなのだ。
生まれたことに意味がなく、存在意義が稼働していない。
だというのに、泣き叫ぶことも悔やむこともできない。
ただ、虚ろな目で見つめるだけしかできない。
……いや、本当にそうだろうか?
生まれた瞬間から「死」という確実な未来が眼前にあったジーク。
間もなく訪れる死の恐怖とともに、問わねばならない大きな問題がジークに迫ってきます。
生まれたことに意味がなく、存在意義が稼働していない。
本当にそうだろうか?
ホムンクルスとして生まれたから。
消費されるために生まれたから。
自分が生まれた意味はないのか。
本当にそうなのか。
この世界にも、歴史をたどれば生まれたときから人権を奪われていた奴隷と言われる人々がたくさんいました。
(現代も同じような生き方を強制されている人がいる国もあるでしょう)
奴隷には生まれた意味はないのでしょうか。
意味があったからこそ、権力によって人権を奪われる人々が無い世界を実便するために人類は努力してきたのではないでしょうか。
現代社会で毎日を生きる私たちにとって、生まれた意味を考える機会はそうそうありません。
明日の仕事の会議や納期、次の休日に行きたい旅行先…
生きていることが当たり前になっている私たちは生まれた意味を普段考えることはないでしょう。
しかしジークのように、生まれた瞬間からすぐに死ぬことが分かっていたら、生まれた意味を問わずにいられなくなるはずです。
そしてその問いは、本当に死が差し迫ったときに考えても間に合わないのです。
生まれた瞬間に自分の問題としての「死」と向き合ったジークにとって、生きていく上で死ぬまでに答えを得るべき、これ以上の問いはありませんでした。
仏教では、「無常」つまり死を自身の問題として向き合ったとき、生きていく上で本当に大切なことが見えてくると教えられます。
彼は思う、必死になって考える。
自分は本当に何もできないのだろうか。
何もできないと、そう思い込んでいるだけではないか。
現に、自分には他の者にはできないことができている。……少なくとも、情報を獲得し、思考して、出した結論に恐怖する。
そこまで辿り着くことはできたのだ。
ならば。もう少しだけ、もう少しだけ前に進め。
もうすぐ自分は死ぬ。
死と向き合い、その未来を真剣に見つめたときジークは「Fate」つまり運命を切り開いていきます。
次回に続きます。
※ストーリー紹介は『Fate/Apocrypha vol.1「外典:聖杯大戦」(東出祐一郎・TYPE-MOONBOOKS)』から引用させて頂きました。
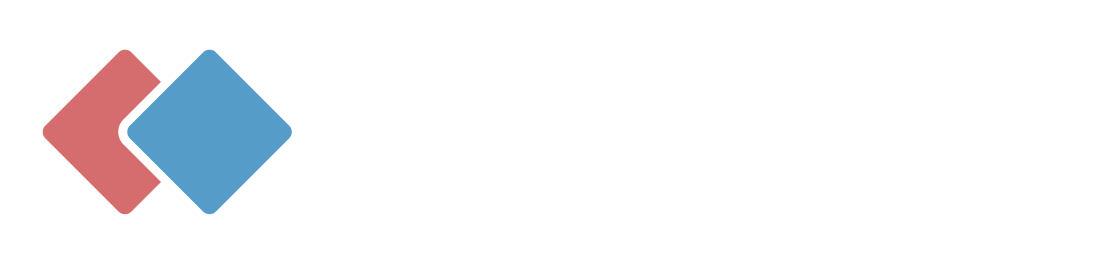












-485x323.jpg)